こんにちは、アマチュア読者です!
今回は、塩野七生『皇帝フリードリッヒ二世の生涯』をご紹介します。
著者はイタリアのローマに長く在住し、西洋の歴史を題材とした数多くの著作で知られています。
文献の深い考察や現地調査をもとに、扱う時代や歴史的人物を丁寧に描き、その読みやすい文体は多くの塩野七生ファンを捉えて離しません。
本書『皇帝フリードリッヒ二世の生涯』では、十三世紀に活躍した神聖ローマ皇帝、シチリア王のフリードリッヒ二世(イタリア語読みではフェデリーコ二世)が成し遂げた数々の功績や、彼が生きた中世という時代が存分に語られています。
「中世最初の近代人」と呼ばれる彼を記念する石碑には、同時代に生きた修道士マシュー・パリスによって次のように書かれています。
この年、皇帝フリードリッヒが死んだ。世俗の君主の中では最も偉大な統治者であり、世界の驚異であり、多くの面ですばらしくも新しいことを成した改革者であった。
この文章の「STVPOR MVNDI」(世界の驚異)が、以後のフリードリッヒの代名詞になります。
「ストゥポール・ムンディ」と言うだけで、ヨーロッパの教養人ならば誰のことかわかるといいます。
1194年にイタリア半島のふくらはぎにあたるイエージという小さな町でフリードリッヒは生まれました。
母が旅路の途中で産気づいて立ち寄ったこの街で生まれた彼は、大変な運命を担っていました。
父がドイツ王でローマ皇帝ハインリッヒ六世、母はシチリア・ノルマン王国の後継者コンスタンツァ。
したがって、フリードリッヒはローマ教皇領を除いた全イタリアとドイツの主君として生まれたことになります。
しかも四歳にして父と母を相次いで亡くし、天涯孤独の身になってしまうのです。
母コンスタンツァは、一人息子の安全をローマ法王インノケンティウス三世に託しました。
いかなる無法者といえども容易には手を出すことができなかったのが中世という時代であり、法王が第四次になる十字軍で頭がいっぱいであったことも幸いして、フリードリッヒは実質ほったらかしにされます。
好奇心の塊であったフリードリッヒは、幼少期をシチリアの首都パレルモで過ごしますが、この時代のパレルモは、当時では異色の社会を構成していました。
カトリック・キリスト教徒でイタリア化して久しいノルマン系シチリア人、ギリシア正教を信仰し続けるギリシア系シチリア人、そのうえイスラム教を信仰するアラブ系シチリア人の三者が混然一体となって暮らしていたのです。
天涯孤独となってからの十年間、フリードリッヒはこの刺激に満ちた環境で、家庭教師に「不屈の精神旺盛にして、万事につけて御しがたし」と言わしめるほど心の赴くままに独学して過ごします。
言語ついては特筆すべきほど習得しています。
中世の国際語であったラテン語、十字軍の公用語であったフランス語、父方の縁から不可欠なドイツ語、母方からと住んでいる土地からも必須であるイタリア語、古典の書物から学ぶために必要なギリシア語、そして街中で自然に耳に入ってくるアラビア語。
若い十年間に様々な言語を習得したことは、のちにフリードリヒがシチリア王、神聖ローマ皇帝として即位した後におこなった数多くの外交において抜群の効果を生むことになります。
無政府状態になっていたシチリア王国内の封建領主たちとの折衝や、ドイツの選帝侯たちとの会談、さらには十字軍における無血での聖地エルサレム奪還に至るまでのスルタンとの外交において、現地の言語を巧みに操り、交渉を有利に進めたのです。
フリードリッヒ二世の生涯を追うなかで、まず強烈なインパクトを受けるのがこの言語の才能ですが、もちろんこれは彼の魅力のほんの一部にすぎません。
フリードリッヒ二世は、ローマ法王と激突を繰り返し、三度も破門されます。
また、宗教にとらわれない俗界の教授陣で構成されるナポリ大学(現在のフェデリーコ二世大学)を創設します。
さらにシチリア王国の封建社会を中央集権の国家に変えるため、法の支配を目指した『メルフィ憲章』も発布します。
本書『皇帝フリードリッヒ二世の生涯』を読むことで、フリードリッヒ二世の人物としての魅力や中世という時代の特徴について、多くのことを学べます。
ぜひ読んでみてください!




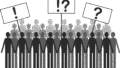
コメント