今回ご紹介するのは、アルベール・カミュの『ペスト』です。
著者はフランス文学を代表する作家として活躍し、1957年には44歳の若さでノーベル文学賞に輝いています。
「不条理」をテーマとした作品を多く生み出し、本書もペストという目に見えない脅威に翻弄されながらも、それに向き合わざるを得ない人間の心理が見事に描かれています。
医師であるリウーの視点で書かれた本書は、感情に流されず、起こったことをあるがままに見る姿勢が貫かれています。
フィクションであるにもかかわらず、あたかも歴史の一次資料を読んでいるかのような錯覚に陥ってしまいます。
ストーリー
医師リウーはある日、鼠の死体をいくつか発見します。
その数は日に日に増していき、ラジオ放送で報告されるまでになります。
その影響は次第に人間にも及んでいきます。
首やわきの下、鼠蹊部に腫瘍ができ、医師の手を尽くしても亡くなる人が続出します。ペストが発生したのです。
原因がわからず、罹患すれば隔離されて激痛に耐えながら死に至らせるこの病気は、人々を恐怖のどん底に陥れました。
頼みの綱は医師ですが、対処法がなかなか見つからず、懸命に治療を施しても命を落とす人をどうすることもできない無念さが本書から伝わってきます。
その後、猛威をふるったペストは突然退潮し、それまで明日がどうなるかわからなかった人々には希望が生まれます。
感染拡大を防ぐために、分断されて生活を余儀なくされていた人は家族や恋人に再会することができ、街は歓喜に沸きます。
その中で、医師リウーはこのペストの記録を書き綴ろうと決心し、物語は幕を閉じます。
医療従事者の奮闘と苦悩
睡眠時間を削りながら患者に向き合い、過度な疲労から周囲への関心がなくなっていく描写は、読んでいて辛いところがありました。
たとえば、それまで、ペストに関心のあるあらゆる報道に対して活発な関心を示していたのに、そういったことを気にかけなくなってしまうこと。
新聞も読まず、ラジオも聞かず、仮に誰かが結果の報告をすると、興味を持つようなふりをするが、実際にそれを迎える態度は上の空の無関心。
こういったことは、コロナウイルスの影響下にある現代の医療従事者にも当てはまるのではないでしょうか。
これは疲労がピークを迎える前の場面ですが、リウーの次のセリフは印象に残りました。
しかし、それにしてもこれだけはぜひいっておきたいんですがね―今度のことは、ヒロイズムなどという問題じゃないんです。これは誠実さの問題なんです。こんな考え方はあるいは笑われるかもしれませんが、しかしペストと戦う唯一の方法は、誠実さということです。
リウーは先が見えないペストの暴虐に対して、自分の役割はもはや治療することではなく、診断することであると悟ります。
発見し、調べ、記述し、登録し、それから宣告するというのが彼の務めになっていました。
患者の家族が泣きわめく中でも、隔離を宣言するために彼はそこにいました。
彼が毎日人々に与えているものは、救済ではなく、知識でした。
高い志をもって医療現場に関わっている人でも、コロナ禍で同じような状況に見舞われているかもしれません。
恐怖にさらされて死者が続出する状況では、人間らしい職務を遂行する余裕は残されているのだろうかと考えさせられます。
ペスト
本書はペストを文字通り、猛威をふるった感染症とみなして読むことができます。
もちろん、コロナウイルスに置き換えても読めるでしょう。
しかし、本書の秀逸さは、ペストを戦争や生活環境など、不条理な境遇と捉えても読み通せるところにあると思います。
あるとき突然はじまって、非道と暴虐のかぎりを尽くした挙句に突然終りを迎える不条理は、人間ひとりの努力ではどうにもなりません。
そういったときに、人はどのようにふるまうのかを本書は教えてくれます。
さまざまな選択肢がある中で、わたしたちはどのような言葉を選び、行動するのか。コロナ禍だからこそ、読む価値が一層高まっている本だと思います。
ぜひ読んでみてください。

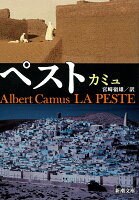


コメント