こんにちは、アマチュア読者です!
今回は、歴史家E.H.カーのおすすめ名著をご紹介します。
著者のエドワード・ハレット・カー(Edward Hallett Carr)は、E.H.カーの名称で親しまれています。
彼は1892年にロンドンに生まれ、ケンブリッジ大学で古典学を専攻します。
超秀才であり、外交官を20年間経験したのち大学の国際政治学教授に任用され、イギリスで創刊された世界最古の日刊新聞『The Times』の編集も担当しています。
しかし自らの思想と当時の政治情勢のすれ違いから職を追われ、7年間の失業も経験しています。
著作を読むとわかるとおり、著者の持つ知的教養は広大で、その鋭い洞察力と書きぶりは読者を圧倒します。
今回ご紹介する作品は、後世に読み継がれてほしいものばかりで、人間がもつ普遍的な特徴について立ち止まって考えさせられる機会を与えてくれます。
『ドストエフスキー』
本書は国際政治学を専門とし、歴史に関する洞察も深い著者によって書かれたドストエフスキーの伝記であり、彼のデビュー作でもあります。
ドストエフスキーが1821年に生まれてから1881年に亡くなるまで、著作はもちろんのこと、彼が書き残した数々の手紙をひもとき、ドストエフスキーの人生や彼が世の中に与えた影響について、著者ならではの客観的で深い洞察がなされています。
多くの伝記というものは、伝記作家の主観が強く反映され、必ずしも対象人物の姿を正確に記しているわけではありません。
しかし、本書の著者であるE.H.カーは、ケンブリッジ大学を卒業したあと外務省に約20年勤務し、ソ連やロシアについて実務を通じて深く理解していました。
ドストエフスキーに限らず、ツルゲーネフやゴーゴリーといった文豪も渉猟し、広い視野を持ってドストエフスキーを捉えていることが本書の端々から感じられます。
当時の政治情勢や社会情勢、分断の状況を客観的に描写し、できうる限り事実にもとづいた記述を心がけていることも伝わってきます。
ドストエフスキーは書簡体の短い小説『貧しい人々』が批評家たちによって称賛されたものの、そのあと長きにわたって世間から注目を浴びるような名作を生み出すことができませんでした。
そのあいだに色恋沙汰や生活における困窮、政治体制を批判するような文章を投稿した廉によるシベリア流刑と、苦悩や絶望に打ちひしがれるような経験を数多くしています。
本書を読むと、そういった経験が後の『罪と罰』『白痴』『悪霊』『カラマーゾフの兄弟』へとつながっていったことがよく理解できます。
ドストエフスキーが幼少期に送った都会での生活が、その後の彼の作品にいかに影響を与えたかをE.H.カーが考察している箇所も非常に読み応えがあります。
「ドストエフスキーほどに「付随的な」人物の想像が貧弱な小説の大家はないであろう」とは著者の言葉です。
その他にも、「西欧人が行動を称賛する一方でロシア人は感情を重視するという価値観の違いがドストエフスキーの作品にあらわれている」という著者の慧眼に思わず唸り、ドストエフスキーの恋愛・結婚経験がどの名著に影響を与えたのかを丁寧に考察する姿勢には襟を正す思いがします。
人物としてのドストエフスキーはもちろん、他の文豪たちとの違い、ロシアと西欧の比較など著者ならではの鋭い洞察が光る作品です。
詳しくはこちらの記事に書いているので、ご参考になさってください。
『カール・マルクス その生涯と思想の形成』
本書は著者によるカール・マルクスの伝記です。
執筆当時、マルクス主義者は、マルクス主義が天から降って来たように、あるいは女神アテナのように親の頭から完全に武装して飛び出してきたように思い込んでいると著者は懸念し、そんなふうに決め込むことは根本的に非マルクス主義的であると考えていました。
なぜなら、「どんな形態の思想もそれを生んだ時代の社会的諸条件である」というマルクス主義的法則の作用を、マルクス主義だけが受けないものと見るべき理由はないからです。
ここに著者がマルクスの伝記を重要と見る所以がありました。
マルクス主義に内包される熱烈な義憤や経済的前提について、それが根を下ろしている土壌に関する何らかの知識を持たずに理解することは不可能です。
「マルクスの伝記を書く者は、マルクス主義を無視することはできないし、無視すべきではない」と著者は強く意識していました。
本書における著者の一番の目的は、マルクス主義を解明したり批判したり反駁することではなくて、いかにしてそれが現にあるがごときものになったかを明らかにすることにあります。
マルクスの家族の系譜や大学での法学・哲学への傾倒、ライン新聞で物怖じしない強硬な姿勢を貫くジャーナリストとしての活躍。
さらには生涯の親友となるフリードリッヒ・エンゲルスとの出会い、ラサールやバクーニンとの関係、結婚生活における経済的困窮など、カール・マルクスが人生を歩む中でその思想はどのように醸成されてきたのかを追体験することができます。
マルクスが残した膨大な量の手紙を読み解きながら、その生涯を丁寧に記した本書の価値は時代を超えて読み継がれる秀逸さを持っています。
『危機の二十年』
著者は大学卒業後、外務省に約20年勤務し、1936年にはウェールズ大学教授に就任します。
その翌年の1937年に本書は企画され、2年後の1939年に第二次世界大戦が勃発する直前に印刷所に送られ、内容の修正をおこなうことなく初版が出版されました。
「危機の二十年」というのは、第一次世界大戦が終戦してから第二次世界大戦が勃発する間の20年を指します。
「将来の平和を築き上げる人々にとって、この20年ほど研究に値する歴史的時代はない」と著者は序文に書き記しています。
本書はユートピアとリアリティという2つの概念のせめぎ合いに焦点が当てられています。
ユートピアニズムは「願望は思考の父である」という言葉に象徴されているように、まず成し遂げたい欲求があり、それが目的となって思考を規定します。
健康を増進したいという目的が医学を生み、橋を建設したいという目的が工学を生み、政治体の病弊を治癒したいという目的が政治学を生み出しました。
ユートピアニズムは、事実や因果関係の分析よりも目的を達成するための概念的な計画を練って行動し、その計画が単純で完全無欠であるために普遍的に大衆に訴えかける力を持っています。
人間の精神は必ずしも論理的な順序で発展していくわけではなく、分析のあとに目的が決まるはずが逆向きに働くこともあるのです。
これに対して、思考が願望に与える衝撃を本書ではリアリズムと定義しています。
ユートピアニズムの夢のような願望とは対照的に、事実の容認や事実の原因・結果の分析に重きをおくリアリズムは批判的で冷笑的な印象を与えます。
リアリズムは客観性を信奉しますが、行き過ぎると不毛になり、行動の活力を奪って人々の意欲をくじきます。
未成熟な思考は目的に目が向きすぎてユートピア的になりますが、目的をまったく拒む思考では老人の思考になってしまいます。
成熟した思考は目的と観察・分析を併せもち、健全な政治思考および健全な政治生活はユートピアとリアリティがともに存するところにその姿を現すというのが著者の考えです。
両者のバランスを上手くとることの重要性とその難しさは、本書の中で何度も説かれています。
ユートピアとリアリティの対立は避けて通ることはできず、完全にこの均衡に達することはないものです。
何が存在すべきかに深入りし、何が存在したのか、何が存在するのかを無視する傾向のユートピアニズム。
かたや何が存在したか、何が存在するのかということから、何が存在するべきかを導き出す傾向のリアリズム。
この2つの思考形態は、あらゆる政治問題に対して相反する立場をつくりだします。
本書ではこれら2つの概念の歴史的背景や基盤を考察し、両者が国際政治にどのように関わってきたのかに焦点を当て、国際政治における権力や法、紛争解決について吟味しています。
これは個人的な経験になりますが、その洞察力に圧倒され、著者の他の作品にも手を伸ばすきっかけになった一冊です!
詳しくはこちらの記事でも紹介しているので、ご参考にしてみてください。
『革命の研究』
本書はイギリスの文芸雑誌”The Times Literary Supplement”に掲載されていた諸論文をまとめて刊行されたものです。
この雑誌は作家のT.S.エリオットやヘンリー・ジェームズ、ヴァージニア・ウルフといった有名な作家が作品を寄稿していたことで有名です。
おもに19世紀から20世紀における社会主義の革命家が世に問うた思想が数多く紹介されています。
人物に焦点が当てられており、思想だけでなく革命思想家の歩んだ道のりも知ることができます。
本書でおもに紹介されている革命思想家は以下のとおりです。
・プルードン
・ヘルツェン
・ラッサール
・プレハノフ
・レーニン
・ソレル
・スターリン
大胆な者だけが公然とマルクスを「修正」しようと企てた。利口なものはマルクスを解釈した。かくして『共産党宣言』は生きた文書として現存している。
E.H.カー『革命の研究』
『新しい社会』
本書『新しい社会』は、1951年に出版された”The New Society”を翻訳したもので、著者がBBCで試みた連続講演の内容がまとめられています。
本書が出版された当時は、大恐慌や第二次世界大戦の影響が残り、近代民主主義の伝統が脅かされていました。
マス・デモクラシー(大衆民主主義)と呼ばれる状況下で、政治組織は商業広告業者を真似てプロパガンダを流通させました。
商品を売りつけるのと同じ方法で、その幹部や候補者を選挙民に売りつけることを考え、国民の理性に訴えるのでなく、国民の軽信性に訴えることにしたのです。
こういった民主主義の実態として、政党が目的を達するために用いているのは、合理的手段ではなくて非合理的手段であると著者は説いています。
現代の政治にも当てはまる部分がありますが、1951年に書かれた内容であることに驚きます。
既存の政治システムが脅かされる社会で、人間が未来を切り開くためには歴史や政治をどのように考えればよいのか。
本書はそのヒントを提示してくれます。
詳しくはこちらの記事で紹介しているので、参考にしてみてください。
『歴史とは何か』
著者は晩年の1961年はじめ、6週連続の記念講演をおこないました。
大学での講演であったものの、教職員や学生だけでなく一般にも公開され、無料で参加できたといいます。
本書はそのときの原稿をもとに、脚注を補って同年末に出版されたものです。
「歴史家とその事実」「社会と個人」「歴史・科学・倫理」「歴史における因果連関」「進歩として歴史」「地平の広がり」という、歴史を考えるうえで重要な6テーマからなっています。
歴史と歴史学の最良の入門書であり、古典的名著です。
「歴史は最大限の反駁すべくもない客観的事実の編纂にあるのではない」という著者の言葉は、歴史を暗記科目と認識している読者には奇異に映るかもしれません。
歴史家には、数少ない意味ある事実を発見し歴史的事実に変えるという課題、次には数多い無意味な事実を非歴史的事実として捨てるという課題があるといいます。
しかし事実とは、広大な、ときにアクセスも難しい大海原を自由に泳いでいる魚のようなものだと著者は言います。
歴史家が何を捕まえるかは、偶然によるところもあるものの、たいていは大海原のどこで漁をするか、どんな道具を用いるかにかかっていて、いろいろやったあげくに歴史家は望んだ類の事実を手にすることになります。
第1講で著者が語る次の言葉を読むだけでも、歴史について興味を搔き立てられるのではないでしょうか。
歴史家と歴史的事実は互いに必要とする関係です。
自分の事実を持たない歴史家は根無しで不毛です。
自分の歴史家を持たない事実は死んだままで無意味です。
したがって、ここまでのところ、「歴史とは何か」という問いに対する私の最初の答えは、こうなります。
歴史とは、歴史家とその事実のあいだの相互作用の絶え間ないプロセスであり、現在と過去のあいだの終わりのない対話なのです。
2022年に出版された新版では、生前に準備していた第2版の序文を新たに訳出し、異版も参照して懇切な訳注や解説が追加されています。
残されたメモから未完の第二版の内容を呈示したR .W .デイヴィスによる覚書、晩年のカーによる自叙伝、略年譜なども加わり、全面的に編集し直されています。
内容を熟知した訳者が労を惜しまず、時代に合わせて読みやすくした新訳によって、著者の名講義が持つウィットに富んだ知的刺激が伝わってきます!
おわりに
今回は歴史家E.Hカーのおすすめ名著をご紹介しました。
著者の持つ広大な知的教養から生み出される鋭い洞察力と書きぶりは、読者を圧倒します。
時代を超えて読み継がれてほしい作品ばかりなので、ぜひ読んでみてください!









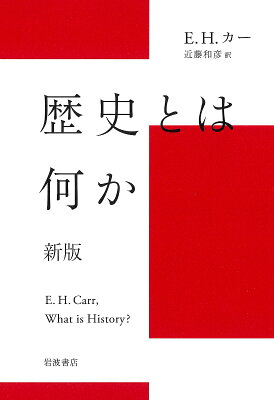


コメント