こんにちは!アマチュア読者です。
今回ご紹介するのは、デヴィッド・グレーバー『ブルシット・ジョブ クソどうでもいい仕事の理論』です。
著者は1961年ニューヨーク生まれの文化人類学者です。
ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE)の教授でもあります。
LSEはこれまでに経済、文学において16名のノーベル賞受賞者を輩出している名門です。
デヴィッド・グレーバーは、これまでに現代社会についての批評を含んだ著作を多く執筆しています。
本書はタイトルにもある通り、「クソどうでもいい仕事の理論」という痛烈なメッセージが込められたテーマを扱っています。
たとえば、仕事にやりがいを感じずに働いている人や、ムダで無意味だと思える仕事を抱えている人、あるいは社会の役に立っている仕事をしているのにどうして低賃金なのか悩んでいる人にとっては興味の持てる内容だと思います。
本書は鋭い論考で、それらの問題に根差している原因をあぶり出します。
ブルシット・ジョブとは
著者は仕事に対するやりがいについて、それが社会にとって役に立っているのかが一つの尺度だと述べています。
医療従事者や教師、消防士、料理人などは明確に仕事にやりがいを感じられるのではないでしょうか。
これに対して、本書のメイントピックである「ブルシット・ジョブ」というのは、その存在理由について、その仕事を毎日こなす本人でさえ確信できないほど、完璧に無意味な仕事のことをいいます。
最終的な実用的定義= ブルシット・ジョブとは、被雇用者本人でさえ、その存在を正当化しがたいほど、完璧に無意味で、不必要で、有害でもある有償の雇用の形態である。とはいえ、その雇用条件の一環として、本人は、そうではないと取り繕わなければならないように感じている。
デヴィッド・グレーバー『ブルシット・ジョブ クソどうでもいい仕事の理論』岩波書店
本書では、ブルシット・ジョブを少なくとも6年にわたって、仕事をせずに給料を受け取っていたスペインの公務員が、その時間を使ってユダヤ人哲学者バールーフ・デ・スピノザの著作の専門家となっていたことを取り上げています。
水道局で働いていた公務員が、仕事を6年間サボっても誰にも気づかれずにいたということは衝撃的ですよね。
本書には関係ありませんが、わたくしアマチュア読者はスピノザには疎いため、代表作『エチカ』は読んでみたいと思っています。
ブルシット・ジョブの一例
本書ではさまざまなブルシット・ジョブが挙げられていますが、わたしが読んでみて印象に残ったものを一例としてご紹介します。
その仕事は、学生会館のコンビニでのアルバイトです。
その仕事を実際に経験した学生が研修後に渡された業務評価は、「顧客へのサービス提供時には、もっと積極的で明るくなければならない」と書かれていたそうです。
機械化が簡単なはずの仕事をやらせたいばかりか、それを楽しんでいるかのようなフリをさせたいのだというのが学生の気持ちでした。
本当に忙しくなる昼休みの時間帯であれば、時間の過ぎるのが早いので耐えられるけれど、誰も学生会館に出入りしなくなる日曜日の午後にシフトが入っていると、彼はただただぞっとしました。
店内がガラガラだったとしても、何もさせてもらえないのが嫌でたまらなかったのです。
レジ前に座って雑誌を読むことはできないし、経営者は完全に無意味な仕事をでっち上げてやらせました。
例えば、店の中をくまなく回って、商品が賞味期限内にあるかチェックさせたり(回転率が良いので、期限内であることはわかっています)、すでにきれいに整頓されているにもかかわらず、他の製品を並べ変えさせたり。
なかでも一番最悪だったのは、考えごとをする時間がたっぷりありすぎたことだといいます。
というのも、その仕事には頭を使う必要がまったくなかったからです。
だから彼は、自分の仕事がどれほどブルシットなのか、どうすれば機械がやってくれるのかを余りある時間で考え続け、その仕事が自分をどれほど惨めなものにしているのかを思わずにはいられなかったといいます。
本書には他にも数多くのブルシット・ジョブが挙げられているので、読者一人ひとりが思い当たる実例に出合えると思います。
こういった実例を読むことで、自分が仕事に求めているのは何なのかを見つめ直す機会が生まれるはずです。
シット・ジョブ
本書では、割に合わない仕事を「シット・ジョブ」と呼んでいます。
ブルシット・ジョブは大抵、とても実入りが良く、極めて優良な労働条件の下にありますが、その仕事の意味がないというのが重要な特徴です。
一方で、シット・ジョブは普通、ブルシットなものではまったくありません。
つまり、一般的には、誰かがなすべき仕事とか、はっきりと社会を益する仕事に関わっています。
ただ、その仕事をする労働者への報酬や処遇がぞんざいなだけです。
先ほどの6年間仕事をサボっても気づかれなかったスペイン人公務員のように、ブルシット・ジョブはたとえ報酬が高くとも、その仕事が社会にとって無意味で、自分に価値を感じられないような仕事です。
そういった背徳感を感じてしまう状況にあるからこそ、ときにブルシット・ジョブをしている人はシット・ジョブに就いている人に攻撃的な態度をとります。
本書を読むまで考えもしませんでしたが、業務内容に虚無感をおぼえている人と報酬や待遇に不満を持つ人のあいだで気分を害するやりとりが行われてしまう社会というのは、もの哀しさを感じます。

数に還元できないもの
『資本論』で有名なカール・マルクスがかつて指摘したように、産業革命以前には、最大の富はどのような条件において作り出されるのかという問題について本を書こうなどと言う発想は、誰の頭にも浮かぶことはありませんでした。
しかし、最良の人間がどのような条件においてつくられるのかー友人や恋人、仲間や市民として共にありたいと言う気持ちを抱かせるような人間を作り出すために社会はどのようにあるべきなのかーについては多数の書物が著されて、現代でも読み継がれています。
アリストテレスや孔子など、日本人でも聞いたことのある歴史に名を残した人々が関心を寄せた問題はまさにこれであって、いまだに重要な問題とみなされています。
人間の生活とは、人間としての私たちが互いに形成しあうプロセスであって、極端な個人主義でさえ、同胞たちからのケアやサポートを通してのみ、個人となります。
「経済」というと、工場モデルに代表されるような数字に還元できて、ドリンク何杯分、ライブのチケット何枚分といった形で換算できるものを扱うイメージを抱きがちです。
しかし、著者は「経済」というのは人間の相互形成のために必要な物質的供給を組織する方法のことであると力説します。
そうだとすれば、「価値」(それは数に還元できないがゆえに価値なのですが)を語るといったやり方で、実際に語られているのは、相互形成とケアリングのプロセスのことなのだと納得できます。
労働について想像したときに、料理人や容姿やマッサージ師を思い浮かべることができる社会になれば、過度に「生産性」や「管理」を重視する必要はなくなり、お互いをより尊重し合える世界になるのではないでしょうか。
数字に還元できるものを信奉しすぎるあまり、文字どおり「プライスレス」な価値のあるものに目を向けられない、あるいは目を向けても意味がないと感じてしまう社会になっているのが大きな問題になっているという著者のメッセージには深くうなずきました。
おわりに
今回は、デヴィッド・グレーバー『ブルシット・ジョブ クソどうでもいい仕事の理論』をご紹介しました。
わたしは本書を読んで、仕事に対する考え方を見直し、自分の本当にやりたいことについて考える時間をつくることができました。
本書に数多く掲載されているブルシット・ジョブの実例を読むと、楽しく仕事をすることをこれまで以上に心掛けるようになります。
ボリュームはありますが、得るものも非常に多い作品です。
ぜひ読んでみてください!
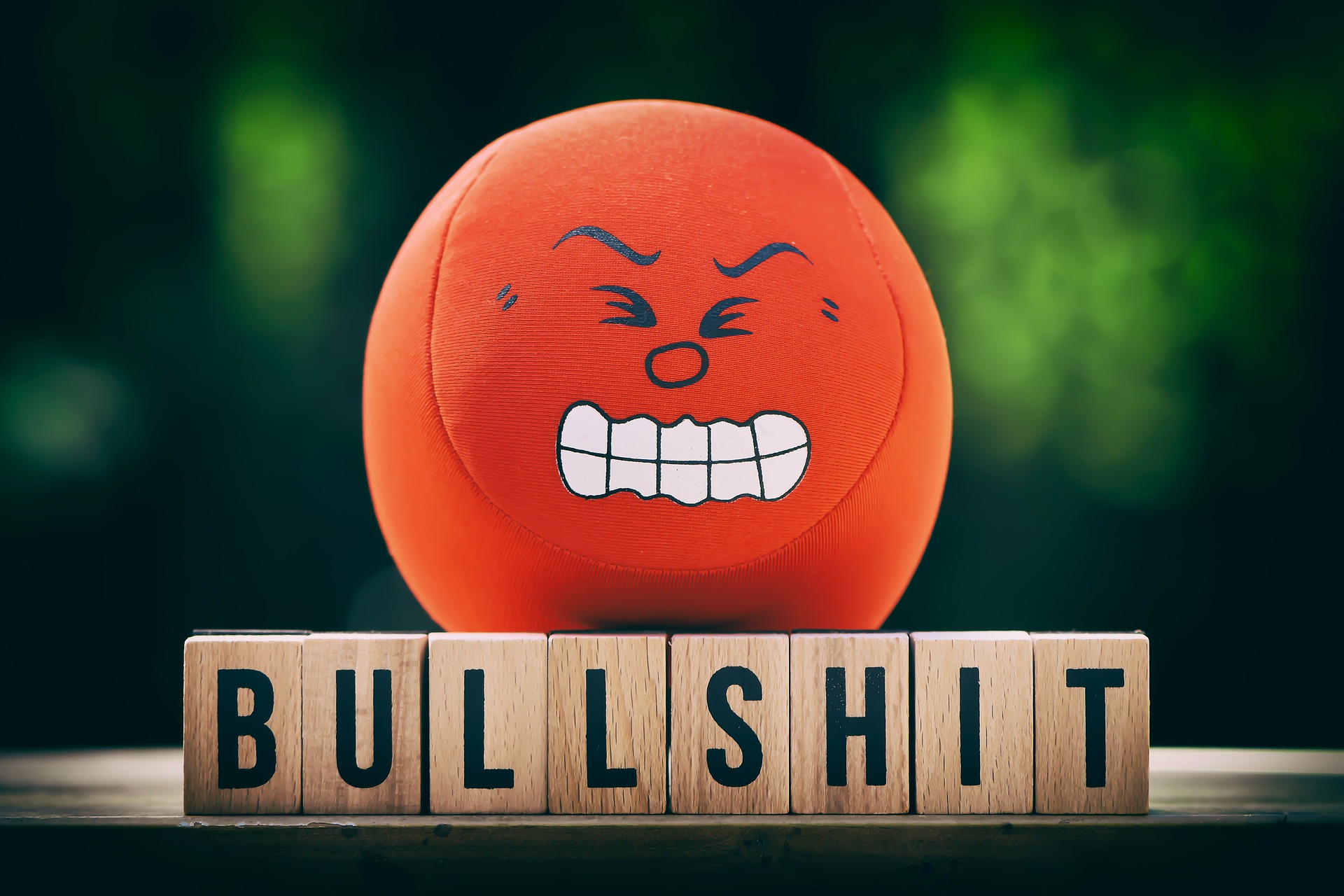




コメント