こんにちは、アマチュア読者です!
今回は解剖学者の養老孟司のおすすめ名著をご紹介します。
出版された順に掲載しているので、著者の作品は興味があるけれど「どの本から読んだらいいのかわからない」「読む順番がわからない」方にはご参考になるかと思います。
著者の作品をたくさん読んできた方にとっても「こんな作品があったのか!」と嬉しい発見があるかもしれません。
著者は1937(昭和12)年、鎌倉に生まれました。
東京大学医学部を卒業後、解剖学研究室に入り、長年にわたって解剖学者として活躍しますが定年を前にして退職し、執筆業に専念します。
解剖学や脳科学の観点から日本社会の問題点を深く考察し、数々の書籍が出版されています。
対談や鼎談の形でまとめられたものを含めると、その数は200冊以上です。
2003年に出版された『バカの壁』は、その年の流行語大賞にも輝くほどのインパクトを世間に与え、これまでに450万部を超えるベストセラーとなっています。
著者は虫採りに熱心なことでも知られています。
幼い頃から虫採りが好きで、文章を追っていると虫を追いかけて動き回っている様子が目に浮かびます。
特にゾウムシに対する興味は人並外れています。
ゾウムシは昆虫のなかで一番種類が多い甲虫に属し、その中でもいちばん種類が多いグループだといいます。
毎年のように新種が発見され、まだまだ調べることが多く残されているのだそうです。
著者はしばしば虫採りを引き合いに出し、自然に身を置くことの重要性を説きます。
採集した虫の標本をつくる様子は動画で観ることができます。
虫を詳細に観察し、標本をつくり、個体の違いについて考えることを通じて「ものを観る眼が養われた」ということは、多くの著作に書かれています。
大変な読書家でもあり、毎日新聞に掲載されていた書評を集めた作品も出版されているほどです。
著者が読んでおもしろかった本は著作で紹介されており、実際に読んでみるとどれもおもしろい本ばかりです。
都市と自然、意識と無意識といった対立する2つの概念を軸に展開される「養老節」は、現代社会において忘れてはならないことを読者に訴えかけます。
- 『唯脳論』
- 『異見あり』
- 『手入れ文化と日本』
- 『養老孟司 ガクモンの壁』
- 『記憶がウソをつく!』
- 『超バカの壁』
- 『脳と魂』
- 『虫眼とアニ眼』
- 『虫捕る子だけが生き残る』
- 『読まない力』
- 『養老訓』
- 『養老孟司の大言論Ⅰ 希望とは自分が変わること』
- 『養老孟司の大言論Ⅱ 嫌いなことから、人は学ぶ』
- 『養老孟司の大言論Ⅲ 大切なことは言葉にならない』
- 『バカなおとなにならない脳』
- 『日本のリアル』
- 『庭は手入れをするもんだ』
- 『バカの壁のそのまた向こう』
- 『身体巡礼』
- 『「自分」の壁』
- 『希望のしくみ』
- 『無知の壁』
- 『日本人はどう死ぬべきか?』
- 『インテリジェンスの原点』
- 『文系の壁』
- 『虫の虫』
- 『「身体」を忘れた日本人』
- 『老人の壁』
- 『超老人の壁』
- 『「他人」の壁』
- 『虫とゴリラ』
- 『まる ありがとう』
- 『子どもが心配』
- 『地球、この複雑なる惑星に暮らすこと』
- 『ものがわかるということ』
- 『日本の進む道 成長とは何だったのか』
- 『日本の歪み』
- 『生きるとはどういうことか』
- 『ヒトの幸福とはなにか』
- 『こどもを野に放て!』
- おわりに
『唯脳論』
著者は、「ヒトの活動を、脳と呼ばれる器官の法則性という観点から、全般的に眺めようとする立場」を唯脳論と定義します。
本書を読むと、私たちがいかに脳を中心とした社会に生きていて、身体を抑圧しているのかがよくわかります。
ここ数万年のあいだに人間の脳が進化していないことを考えると、脳と身体、あるいは都市と自然という対立はヒトに宿命づけられた問題です。
脳科学といえば理系の分野だと思われるかもしれませんが、言語は感覚性言語中枢から運動性言語中枢へ抜けて、運動器によって外部に表出されることを考えるだけでも、学問は脳の法則性の支配下にあるのです。
内容は簡単ではないのですが、写真や図が多く掲載されているので飽きずに読み通せます。
読めば読むほど味が出る、社会の本質を突く論考です。
『異見あり』
本書は1997年から2000年にかけて、著者が様々なメディアに対して執筆したエッセイをまとめたものです。
「自分の生き方が、そのまま自分の意見になり異見になる。それ以外に意見のありようなどないはずである。」という冒頭の言葉にさっそく引き込まれます。
しかし本書で著者が綴る社会に対する考えを読むと、「異見」と表現するのに相応しい独自性が発揮されています。
東京大学医学部時代から組織と距離を置いていた著者の視点は、鋭く社会をとらえます。
現代のように組織化された社会は意識の産物であるために、無意識がのびのびとはたらく余地が残されておらず、よく組織化されているだけに逆にさまざまな面で配慮が不足する社会である。
こういった著者の考えは、ビジネス書や自己啓発書に親しんでいる方には新鮮に感じられるのではないでしょうか。
著者の「私はシラバスも作らず、自己評価もしない恩師に教育を受け、いまでも師を尊敬している。それは私が唯一、大声でいえることである。」という言葉は、無意識に人の内面まで規制してしまう社会に警鐘を鳴らしています。
何年たってもリーダブルな論考が満載です。
アナウンサーの古舘伊知郎氏による本書の解説も非常におもしろいです!
『手入れ文化と日本』
人間が手入れした自然にこそ豊かな生命が宿るという日本古来の思想をはじめ、子育てや教育、心とからだについてなど、現代日本社会を説いた8つの名講演がおさめられています。
講演録であるため、著者が語りかけるような文体で読みやすいです。
本書が出版されたのは2002年ですが、今日でもなお、その内容には普遍性があります。
現代人にとって、知ることは自分とは独立したもので、すべてノウハウ、自分とは関わりのないこと、しかしそれを知っていて操作できる関係であると著者は語ります。
しかし自分と独立した「知」というのはありえないことで、たとえば重篤な病気を告知されると、告知される以前の自分と告知された後の自分は違うものになります。
そうやって何かを自分と関連づけて、本当に自分のものとして知れば、自分が変わってくる。
自分が変わるということは、過去の自分が部分的に死んで、新しい自分が生まれるという著者の言葉は、都市化、情報化、脳化した社会で、自分が変わる経験ができない現代人の特徴とは対極にあるといえます。
自然に親しむ環境であれば、不幸な出来事が起こると「それは仕方がない」となりますが、都会の中で不幸な出来事が起こると「誰のせいだ」ということになります。
そう考えると、日本人が変化したのではなく、日本が都市に変わったから責任を強調する社会になったのだと腹落ちできます。
便利な世の中になったように思えて、じつはあちこちで綻びが出ているというのがいまの日本社会なのだということが本書を読むとよく理解できます。
『養老孟司 ガクモンの壁』
著者と第一線で活躍している若手科学者とのおもしろ対談集です。
ネアンデルタール人と現代人は何が違うのか、クローンとは何か、視覚や聴覚はどう認識されるのか、人はなぜ超常現象を信じるのかなど、文系と理系の壁や学問領域を飛び越えた内容で話が進みます。
考古学者、心理学者、脳科学者、言語人類学者、神経行動学者、生物学者など様々なバックグラウンドを持つ科学者の話だけでも刺激的ですが、それぞれのトピックに対する著者の考えや知見も非常に刺激的です。
たとえば考古学者が古代人の残したものを扱うとき、それにどんな意味を与えるかに非常に困るということに対して、次のように回答しています。
「見ただけでは用途がわからない物を作り出すのが現代型人類の特徴で、事物を抽象化してシンボル体系を作り出すという脳の働きの現れだ。そういうときには、解釈する人が物語を作っていくしかないし、たくさんの物語があることが人生を豊かにしていることを認めればいい。」
著者の底知れない教養が垣間見えます。
それだけでなく、本書の中でたびたび目にする、解剖学に長いあいだ従事していた著者がもつ身体に関する知識や深い考察にも唸るばかりです!
『記憶がウソをつく!』
著者とアナウンサー古舘伊知郎氏の対談本です。
著者の自宅で行われたこの対談は、記憶や脳についての話が中だるみすることなく、テンポよく進んでいくので読んでいて心地よく感じます。
やはり弁が立つ古館氏の話が長いのかと思いきや、著者も長広舌をふるい、文章のみからであるものの、おたがいに会話を楽しんでいる様子が伝わってきます。
インタビューやシンポジウムのような硬い雰囲気の場では生まれない言葉が目白押しです。
「勉強というものは、まず知識を自分のものにする、身に付けることであって情報処理の技法ではない。知識が自分のものにならなければ、けっきょく自分自身が消えてしまって、本当におかしいとか、本当にそうだと思うことがない。」
こういった言葉がふっと出てきます。
同じ意味の話を聞いていても、自分に入ってくる言葉とそうではないものがありますが、本書は「入って来るなぁ」と感じる言葉であふれています。
古舘伊知郎という人物と、著者の自宅という場が触媒になったのかもしれませんね。
『超バカの壁』
本書は先に出版された『バカの壁』『死の壁』に続く、いわゆる「壁シリーズ」の3作目にあたります。
既刊の2冊に対する反響が大きく、「本に書いてある内容を自分に当てはめたらどうなるのか?」という身の上相談が多く届いたといいます。
そうした質問を編集部の方がまとめ、それに答える形で本になったのが本書『超バカの壁』です。
各章が読み切りの形式になっているので、どの章から読んでも楽しめる内容になっています。
若者の問題、自分の問題、男女の問題、子供の問題、金の問題、心の問題など、現代のみならず古今東西において人間がぶつかってきた悩みがテーマになっており、それぞれに対する著者の洞察は非常に深いです。
自分の頭の中に「バカの壁」を築き、その向こう側のことを想像できないために、起きている自分の意識だけが世界のすべてだと思ってしまう著者の考えは、一見当たり前のように思えます。
しかし、本書を読むとこういった「ものの考え方、見方」が如何に根深い社会問題につながっているのかが見えてきます。
その渦中にあるのが自分なのだということにも思い至り、ものの考え方や見方を見直すきっかけにもなります。
読みやすい内容でありながら、新たな発見が多く得られる一冊です。
『脳と魂』
仏教的な考えの著者と、量子力学を交えて仏教思想を論じる禅僧の玄侑宗久氏の対談本です。
玄侑氏は『中陰の花』で第125回芥川賞に輝き、文学作品や『現代語訳 般若心経』をはじめとする一般人向けの仏教書籍を数多く出版されています。
お茶を飲みながらリラックスして話をされている印象を受けますが、話の内容は身体性が消えていき都市化されていく社会の問題をはじめ、世間と個人、科学至上主義の側面など、かなり込み入っています。
都市化の問題についていえば、わたしたちは基本がまずあって、そこから応用へと進んでいくのが正しいと考えますが、現実には応用しかなくて、様々な応用から抽出した、どの現実にも属さないフィクションが「基本」であるという考えは日常生活ではまず出て来ないですよね。
そのフィクションを先に学ばなければならないのが「脳化社会」の特徴だというのは卓見で、思わずうなってしまいます。
この著者の意見に対して、玄侑氏も「書道も自然から一番遠い楷書から学ばせますよね。文字ができてきた順番からいうと草書が最初のはずなんですけど。」とすかさず返すところも素晴らしいです。
本書は流れるような話が進んでいきますが、脱線しているようで気づけば深いところまで降りていて、振り返ってみると螺旋階段だったということが頻繁に起こる面白い作品です。
『虫眼とアニ眼』
著者とスタジオジブリの宮崎駿氏が、宮崎作品をとおして自然と人間のことについて対談した内容をまとめたのが本書です。
小さな虫のからだや動きのディテールを捉えて楽しむ著者がもつ「虫眼」と世界に影響を与え続ける宮崎駿氏の「アニメ(眼)」が捉える若者や子ども、現代社会についての意見を読むと目から鱗が何度も落ちます。
「養老さんと話して、ぼくが思ったこと」として宮崎駿氏が描いた20ページ以上にわたる冒頭のカラーイラストと文章は、都市化した社会が抱える問題を平易な言葉で表現しており、いつ読んでも日本や未来の子どものことを考えさせられます。
宮崎駿作品のファンである方にも是非読んでいただきたいです。
本書の後半に著者の宮崎アニメ論が掲載されていますが、次の言葉をはじめ、名言が散りばめられています。
アニメであれ文学であれ、あらゆる芸術表現は、その方法でなければ表現できないものを含んでいる。だから文字にならない、言葉にならないのである。そもそも文字でもなく言葉でもないから、芸であり術なのである。それでなければ、言葉だけあれば十分ではないか。その芸や術を、言葉にして説明されなければ、気が収まらないというのは、典型的な現代病、脳化という病気である。
こういった言葉で出会えるからこそ、養老孟司の作品を読むのはやめられません!
『虫捕る子だけが生き残る』
著者と生物学者の池田清彦氏、フランス文学者で『ファーブル昆虫記』の翻訳も手掛けた奥本大三郎氏の3人による虫をテーマにした鼎談がまとめられています。
本書を読むと、「本当に虫が好きなんだな」ということがよくわかる内容で、虫の話であれば何時間でもしゃべっていられるのだろうと思ってしまうほど楽しそうなことが文章から伝わってきます。
自分が興味を持っていなくとも、好きなことを楽しそうに語り合っている作品というのはおもしろいもので、著者たちの楽しさが読者の側にも移ります。
こういった内容にもかかわらず、教育論や環境論、虫と共生する未来についても語り合っているところに多くの発見があります。
虫には、採る、集める、調べるという3つの楽しみがあり、お金がほとんどかからないことが特徴的だといいます。
お金だけ使って、頭と体をまったく使わない遊びと違って、虫採りは、お金は不要なかわりに頭と体をイヤというほど使う究極の遊びだというのが池田氏の意見です。
虫を見たり採ったりしていると、自分の先入観が壊れる新しい発見が絶えずあるといいます。
世界のディテールを見て、感じることで自然に自分なりの価値基準ができあがり、それが個性になるという話は非常に興味深いです。
『読まない力』
タイトルの『読まない力』は、どこまでものごとの予想をするのか、どこまで言葉そのものの重みを信じるかという本書の内容を指しています。
雑誌『Voice』に書き連ねた時評がまとめられており、過去の出来事に対して著者の感じたことを追体験できます。
オリンピックや北朝鮮問題、少子化など現代にも通じるテーマについての著者の見解は普遍的であり、自然を軽視しがちで「ああすれば、こうなる」を信奉する現代人にはいつまでも残る課題にふれています。
戦後の都市化の過程で、日本人は徹底的に自然を破壊してきました。
その結果としてものの考え方も変わり、「ああすれば、こうなる」世界を重視し、感覚が消された数字が信頼され、自然な子どもを二の次にする社会になっていったという考えには目を開かされます。
各トピックについて2ページの読み切り形式なので、どこから読んでも楽しめる構成です。
『養老訓』
著者の70歳を記念して刊行された、大人のための笑って過ごす生き方の知恵が詰まった一冊です。
本書では9つの訓示が紹介されており、「不機嫌なじいさんにならない」「感覚的に生きる」「夫婦は向かい合わないほうがいい」「面白がって生きる」「一本足で立たない」「こんな年寄りにはならないように」「年金を考えない」「決まりごとに束縛されない」「人生は点線である」と続いていきます。
本書には、著者の読書論についても言及があります。
著者にとって、読書は自分で考える材料であり、自分の見方の参考にするものだといいます。
そう考えると、つまらない本というのはあまりなくなり、自分と異なる考えの本を読んでも「この人はどうしてこんなことを言うのかな?」と考える材料になるというのは目から鱗です。
200ページに満たないコンパクトな作品にもかかわらず、楽しく生きるための考え方がぎっしり詰まっています。
『養老孟司の大言論Ⅰ 希望とは自分が変わること』
季刊雑誌『考える人』に連載した著者の文章を本の形にしたのが本書です。
『考える人』の創刊以来、足かけ9年間にわたって続けた連載のため、3冊に及ぶシリーズになっています。
1冊目のサブタイトルは「希望とは自分が変わること」。
自分は変わらない存在なので未来が不安だという方は、本書を読むと自分が変わるきっかけになるかもしれません。
各地に赴いてつづった紀行文が多く含まれ、他の作品にはあまり見られない著者のプライベートな一面が垣間見れます。
「読む」とはどういうことかについても一章を割いて考察されています。
著者が性格的に「手段としての行為」に耐えられない純粋行為至上主義者だという話は興味深く、著者が読書をすることと一般の人がスマホをいじることは動機としては似ているのではないかと考えさせられます。
違う点は、現代人の時間の多くは「それ自体が目的でない行為」のみになってきていることで、これは社会の変化として捉えなければならない話なのだということにも気づかされます。
著者独特の読書観は、これだけで1冊の本になりそうなほど深みがあります。
本書の付録として、巻末に著者の全著作がリストアップされています。
これまで著者の作品を数多く読んでこられた方も、この一覧を目にして「こんなに多くの著作があるのか!」と驚かれるかもしれません。
『養老孟司の大言論Ⅱ 嫌いなことから、人は学ぶ』
サブタイトルは「嫌いなことから、人は学ぶ」。
戦争や信仰、ユダヤ問題など様々なトピックについて論じられていますが、「同じ」と「違う」についての考察にも紙幅が割かれています。
感覚は主観的なものであり、科学的な客観主義あるいは普遍性とは異なるものだということが深く認識されていないという話には目から鱗が落ちます。
本書の付録として、思想家であり武道家でもある内田樹氏との特別対談が掲載されています。
一般的に当然とみなされている哲学や思想を根本から考え直す作業が忘れられているという話から始まり、定冠詞と不定冠詞の区別、orderという語の根源的な意味、信仰が内面化した人の思想など、おもしろいトピックで話が最後まで展開していきます。
『養老孟司の大言論Ⅲ 大切なことは言葉にならない』
サブタイトルは「大切なことは言葉にならない」。
「日常としての宗教」「科学と宗教と文明」「言葉が力を持つ社会」「自然に学ぶ」など、Ⅰ~Ⅱと同様にさまざまなテーマを著者の視点で深い論考が展開されています。
本書の最後にある「大切なことは言葉にならない」という章では、著者がなぜ考えるのかについて書かれています。
数々の著作を言葉として世に出してきた著者だからこそ、「大切なことは言葉にならない」の重みはいっそう大きくなります。
本書の巻末には、著者のオススメ本リストとして150冊が挙げられています。
生物、哲学、政治思想、ミステリー、小説、古典などジャンルにとらわれないラインナップで、おもしろそうな本ばかりで、「著者はどのような本を読んできたのだろう?」といったことについて興味のある方にはオススメです。
『バカなおとなにならない脳』
小学生、中学生、高校生が投げかける脳や解剖に対する質問や学校生活での相談事に対して、著者が嚙み砕いた言葉で丁寧に回答する一問一答式の作品です。
「バカって治るんですか?」「バカなおとなにならないためには?」「子どもの脳、どうしてキレやすいんですか?」といった素朴でストレートな質問への回答を読むと、深く頷きしばらく考えを巡らせる時間が生まれます。
現代は結果だけを求め、そのプロセスを過小評価する情報化社会であり、著者の言葉でいえば「脳化社会」と表現されます。
その理由の一つとして、家電製品をはじめとする身のまわりのものがスイッチを押すだけで機能する環境で生活していることが挙げられています。
一方で、人生はプロセスそのものであり、無駄かどうかをあれこれ考え過ぎずに、たまにはプロセスをたどれる農作業などに体を使う方がいいと著者は提言しています。
本書を通読すると、子どもの悩みの多くに人間関係が含まれていることがわかります。
学校とその中の人間関係がすべてだと考えてしまい、上手くいかなくなると人生が終わったような気がしてしまう状態はかなり深刻に感じます。
著者は李白の「別に天地あり、人間にあらず」という言葉を引用し、世間以外に天地があり、自然があると説きます。
人間関係で頭がいっぱいになってしまったら、自然に親しんで体を動かすことで気持ちの持ちようが大きく変わるということは、当たり前のことであっても、老若男女問わず覚えておきたい金言ですね。
『日本のリアル』
敗戦時に小学校二年生だった著者は、その社会的な価値の転換を目にして、モノに直接携わることの大切さを身に染みて感じたといいます。
お金だけのやりとりがインターネットの普及で加速している時代に、モノに携わったり、ふつうの日常の研究をしている人に出会うとホッとすると語ります。
本書は、著者が「本当の仕事」をしていると考える4人と対談した内容をまとめたものです。
「家族の絆」の実態を調査し続ける岩村暢子氏。
耕さず、農薬も肥料も使用しない農業で強い米を栽培した岩澤信夫氏。
植林活動で海を変えた牡蠣養殖家の畠山重篤氏。
日本でみられなかった合理的な間伐を普及させる鋸谷(おがや)茂氏。
農業、漁業、林業、食卓というテーマが扱われていますが、どれも私たちの日常生活に不可欠な要素で刺激的です。
お金に執着せず、仕事に入れ込んでいて、ごくふつうの日常に向き合っている対談者の話を読むと「本気で仕事をしてるな」と感じます。
いまの仕事に不満や悩みを感じている方や、どんな仕事をしたら良いか迷っている方にはおすすめの作品です。
『庭は手入れをするもんだ』
サブタイトルに「養老孟司の幸福論」とあるように、本書は現代人に対して厳しいながらもあたたかい著者による励ましの書です。
現在の日本人は、自分が食物からつくり出すエネルギーの40倍もの外部エネルギーを消費しているという試算があるといいます。
自然に考えれば、それだけ身の丈に合っていない生活を送っているということなのですが、現代人はそれに無自覚であるというのが著者の考えです。
たとえていえば、現代人は本来の人間の40倍高い高下駄を履いて、高みに立っているので昔は大きく見えた自然が相対的に小さく見えるようになってしまった。
そのために、自然は自分たちの思い通りになると思うようになったのです。
こうして「自然の価値」が下がってきてしまったことに対して、石油を使い切ってしまうしかないというのが著者の意見です。
石油がなくなると大変なことになるというのが一般的な反応だと思いますが、自然のありがたさを再認識するきっかけになるので、むしろ感謝しなければならないと著者は語ります。
自然への畏敬の念を取り戻すことができれば、自然の一部である人間存在そのものの重みも復活してくるはずだと考えると、希望が持てる考え方に思えます。
地球温暖化やマイクロプラスチックなどが問題となる人新世の時代において、身の丈に合った生活に改めることが一番の近道だというのは、おそらく誰もがわかっていることだと思います。
そのわかり切っていることを行動に起こす契機として、著者の本気の言葉は心に響き渡ります。
本書では自然環境が被っている問題に警鐘を鳴らし、特に森、仕事でいえば林業の歴史的背景について詳しく書かれています。
著者は「都会が家なら、山は庭だろう」と言います。
余裕があったら庭の手入れをするのは当たり前だということです。
「もっと国土に関心をもってよ」という著者のメッセージに頷くばかりの内容です。
『バカの壁のそのまた向こう』
本書は月刊『かまくら春秋』という雑誌で2009年から2013年までに連載された、著者のエッセイをまとめたものです。
著者は鎌倉の地元民であるため、母親の代から『かまくら春秋』に親しんできたといいます。
おもに環境問題をテーマにしているので、他の著書と比較して特に自然についての論考が多いです。
「だれかがやればいいと、世界中の人たちがそう思った結果が、いわゆる環境問題である」
「世界中の責任を、たとえば森が背負っている」
こういった言葉を読むと、現代人が軽視している自然について、立ち止まって考えさせられます。
ただ、立ち止まって考えても自然のことはわからないので、自分で体験することを著者は勧めます。
現代人は、自然を映像化し、言葉にすれば、わかるはずだと思い込んでいる節がある。それって、かなり危ないよなあ。私はいつもそう思う。だから自然について書きたくないのだな、と続いて思う。私の書いたものを読むより、外の自然に自分で触れるのが先じゃないか。そもそも説明が上手なほど、相手は実際を見なくなるはずである。
自然のことをわかった気になっている人にとっては耳の痛い話ですが、実際に自分で体験しなければわからないことの重要性が全体を通して伝わってくるのが本書です。
『身体巡礼』
本書が出版される30年前に訪れたウィーンの教会で、著者はハートに矢が射すようなマーク(著者いわく「変なもの」)をミサの案内の中に見つけます。
日本に戻ってからも、そのマークが意味する「聖心」について考え続けていたといいます。
その興味は尽きず、ウィーンを訪れようと考えていた著者の話を編集者が耳にして、本書が企画されました。
ドイツ、オーストリア、ウィーン各地の教会や礼拝堂、墓地に足を運び、埋葬、ヨーロッパの心臓信仰、現代社会などについて、著者があらためて考えたことが惜しげもなく表現されています。
著者が訪れた名所のカラー写真も多く掲載されているので、読むのに疲れたら眺めて楽しむこともできる作品です。
『「自分」の壁』
著者が長年考えてきた「自分」という問題をテーマにつづったエッセイです。
幼い頃から、自分以外の人たちからできている世間で安心して行動していいのかどうかに不安を感じ、その気持ちはかなりの歳になるまで続いていたと著者は語ります。
折にふれて、そういった自分の気持ちを掘り下げることで、自分とは何なのかを著者の観点でまとめ上げたのが本書です。
周囲が押さえつけにかかっても、それでもその人に残っているものが個性であり、放っておいても誰にでもあるものである。
だから世の中で生きていくうえで大切なのは、人といかに違うかではなく、人と同じところを探すことである。
生物学的にみると、人間のお腹の中には60兆とも100兆ともいわれる数の細菌がいて、それらと共生しているにもかかわらず、「除菌」が当たり前の世の中になっている。
このような共生が自然の本来の姿であるのに、個性を持って確固とした「自分」を確立し、独立して生きるといった考え方が当然のこととみなされているというのは現実味のないものである。
なにかにぶつかり、迷い、挑戦し、失敗することを繰り返し、自分で育ててきた感覚のことを「自信」という。
上述のように、本書には「自分」を壁だと考えて悩んでいる方々にとっては珠玉の言葉が満載です!
『希望のしくみ』
著者とスリランカ仏教界長老のアルボムッレ・スマナサーラ氏の対談本です。
スマナサーラ氏は、主著『怒らないこと』をはじめとして多くのベストセラー作品を残しています。
本書の対談は、近代科学を長年にわたって学んできた著者が、「近代科学の方法を使って自分の頭で考えると、原始仏教の教えと同じになる」という面白い話で始まります。
仏教についての基礎知識がなくとも十分楽しめる作品で、幸せ、知恵、希望など様々なテーマでお二人が語り合います。
知識と知恵についての話は興味深いです。
知識は情報を頭の中に組み込むもの、これに対して知恵は「だから何?」という「問い」に「答えを出す能力」だという話は腹落ちしました。
著者は、日本人に知恵というと不思議なもののように受け取られてしまうので、かわりに「方法」や「やり方」と言わないと伝わらないと語っています。
普段の日常会話では生まれない、知恵の詰まった対談から学ぶことは非常に多いです。
なお、著者の考え方が原始仏教の教えと同じだと気づいたのは、インド哲学者で東洋思想の世界的権威である中村元氏の阿含経の解説書だったといいます。
中村元氏の著作については、こちらの記事をご参考にしてください!
『無知の壁』
『希望のしくみ』と同じく、著者とアルボムッレ・スマナサーラ長老の対談本です。
「自分について考える」ことをメインテーマとし、脳と仏教の観点から「自分をはずす」ことによって楽に生きるためのヒントが詰まっています。
聞き手は宗教学者で住職でもある釈徹宗氏です。
釈氏による対談の進行や質問の仕方、相槌は読んでいて心地よく、本書のおもしろさの1つになっています。
著者は、脳にある枠組みができてしまうと、脳はその枠の外のことをそもそも認識しようとしないことを「バカの壁」と表現しています。
一方で、仏道を「我々がついもってしまっている自分の枠組みを通してしか物事を認識できていないことに、まず気づく。そして、その枠組みをはずすトレーニングを実践する」と捉えると、2人の説いている領域は共通するところが多いという釈氏の観点は印象に残ります。
『日本人はどう死ぬべきか?』
著者と建築家の隈研吾氏の対談本です。
タイトルにある、『日本人はどうやって死ぬべきか?』というのは「どうやって生きていけばよいのか」にも密接につながるテーマです。
本書では、日本人の特徴やうまく年齢を重ねる秘訣など、自分の将来のことに不安を感じている方には心に刺さる言葉が多いのではにないかと思います。
著者の身体についての話は非常に興味深いです。
「体」の語源は「空」で、それを身体と書くようになったのは江戸時代のこと。
「空」のものに身がついてしまい、さらにひっくり返ったのが「心身」という言葉で道元の時代には「身心」と表され、「身」が先に来ていた。
いまはパソコンやスマホで文字変換しても「心」が先にくる社会になっているという著者の指摘には目から鱗がバッサリ落ちました。
本書の最後に隈研吾氏が述べる建築論も一読の価値があります。
わたしたちが当たり前のこととみなしがちな住宅ローンの話にも言及があり、住まいとは何かを考え直す機会を与えてくれます。
『インテリジェンスの原点』
作家の五木寛之氏がホストを務めるトーク番組を書籍化したものが本書です。
著者の虫採りの話や人間の脳の話、敗戦前後の価値観の話など示唆に富む内容ですが、話し言葉で綴られているので読みやすいです。
戦後にそれまでの価値観が音を立てて崩れたことを経験した著者は、言葉に信用を置かず、正しいとか正しくないとかの判断は最終的にモノに落とすしかないと考えます。
著者の場合、その落としどころが「脳」であり、人間の感情や心の動きは脳の問題だと説きます。
著者は「京都国際マンガミュージアム」の館長をつとめていた時期であったこともあり、日本語の構造とマンガ文化の関係を脳科学の観点で語っています。
脳の中では、仮名を読む場所と漢字を読む場所が離れていることがわかっており、著者はこの事実とマンガの関係は深いと捉え、独自の解釈をしています。
マンガが好きな方には気になる話だと思うので、ぜひ読んでみてください!
『文系の壁』
サブタイトルに「理系の対話で人間社会をとらえ直す」とあるように、本書では多くの文系の意識外にある概念について4人の理系の著名人たちと対談した内容がまとめられています。
その4人とは、超人気小説家であり工学博士でもある森博嗣氏、医学博士でありスマホで手軽にVR(バーチャルリアリティ)が体験できる「ハコスコ」の企画・販売・運営をおこなっている藤井直敬氏、天才プログラマーでスマホ向けのニュースアプリ「スマートニュース」を運営している鈴木健氏、毎日新聞記者で2014年のSTAP細胞事件の過程をまとめた書籍『捏造の科学者 STAP細胞事件』で大宅壮一ノンフィクション賞や科学ジャーナリスト大賞に輝いた須田桃子氏です。
健康管理しないほうが長生きするという統計データについての話、文系の方がデジタルであるという話、文系の人の「わかり合えた」は「賛成だ」という話など、文系と理系とを問わず、当たり前とみなしているものごとの考え方について再考させられる内容です。
文系と理系で進路に迷っている学生にもおすすめです。
藤井直敬氏が刊行したVRについての著書『拡張する脳』については、以前に運営していたブログで紹介記事を書いているので、ご参考にリンクを貼っておきます。
『虫の虫』
前半は虫採りエッセイ、後半はラオスでの虫採り紀行文で構成されている本書からは、虫採りの面白さが伝わってきます。
本書の冒頭に著者の虫採り姿がカラー写真で掲載されていますが、「本当に楽しそうだな」ということが一目でわかります!
ラオスでの虫採り紀行の様子は以下の動画で観ることができます。
虫採りは自然を相手にする営みですが、そこで邪魔になるのは自分の勝手な思い込みだといいます。
思い込みが壊れるのも発見の一つであり、発見とはじつは自分に対する発見なのだという深い洞察に著者の凄さがあります。
思い込みとは自分の考えであり、思い込みが壊れるというのは自分の考えが変わり、自分が変わる、極端な場合は「生まれ変わる」ことにつながります。
思い込みが壊れる経験を何度もしていると、その都度生まれ変わるので歳をとらず、頑固にならないという考えを知ると何だか元気が湧いてきます。
著者はさまざまな作品の中で、「頭を良くしたいならば自然に身を置け」と提言します。
本書は、都市化した社会において、自然に身を置くことが人にどう影響するのかが垣間見え、非常におもしろい内容です。
『「身体」を忘れた日本人』
著者と環境保護活動家のC・W ニコル氏による対談がまとめられています。
ニコル氏は、50年前の日本の自然を見て素晴らしいと思ったから日本に移住したといいます。
しかし、「もし、いま日本に来たら日本人はならなかったでしょう。日本はずいぶん変わってしまった。」と日本の環境を憂慮する言葉には重みがあります。
ニコル氏の友人のアメリカの森林監督官が日本の杉の人工林を見て、「花粉が多いのは、成長が止まって苦しいから、子孫を残すために必死で花を咲かせているからじゃないか」と話したエピソードが本書の冒頭にあって印象的です。
現代では花粉症が社会問題にあがるほど深刻で、政治的に花粉症対策に取り組む自治体も増えています。
本書は、花粉症が蔓延するに至った歴史的背景についての話から始まり、子どもの教育のことや動植物のこと、後半では自然を愛する著者とニコル氏が懸念する日本の自然の将来について語り合っています。
最後の「対談を終えて」では、お二人の大切にしている価値観が詰まった言葉に出会えます。
「ここだけでも読んでほしい!」と思える文章です。
写真も多く掲載されているので、ビジュアル的にも楽しめる一冊です!
『老人の壁』
著者と、イラストレーターでありながら古今東西の数々の有名人になりきって人生を送る南伸坊氏のおもしろ対談本です。
親交の深いおふたりということもあり、序盤からかなりフランクな口調でテンポよく会話が進むので、読んでいて心地よいです。
その中でも不意に飛び出す含蓄に富んだ言葉にはっとさせられることが多く、気づけば得るものが多く見つかる作品です。
「本当は勉強や学問って自分が知らなかったことに気づく、それだけなんですよ。そういう楽しみを持たない人が増えたとしたら気の毒ですよね。」
「学んだり発見する喜びは内面にあって他者の評価によらないし、それが人を若々しくしたり幸福にするというのは、本当は当たり前のことなんでしょうけどね。」
こういった言葉を目にすると、思わずページをめくる手を止めて虚空を見つめてしまいます。
「不機嫌社会」と見出しのついた対談では、満員電車に象徴される我慢による不機嫌さから起こる猟奇的殺人について、著者の見解が披露されています。
何も考えなくても楽に暮らせる時代になると、他人が何かに反応しているのを見て、それに反応して自分から何かすることがほとんどゼロになっているとした上で語られる次の言葉は胸に迫ってきます。
自分でやることのある人っていうのは、反応していないんですよ。そうでしょう。自分にやることがないと、他人のやってることに反応するんですよ。
『超老人の壁』
『老人の壁』の続編となる、著者とイラストレーターである南伸坊氏の対談本です。
何気なく雑談している中に、生きるのが楽になるヒントが散りばめられています。
たとえば、生きる感覚が失われていく現代社会の問題です。
建物の中でずっと仕事をしていると、明るさは変わらない、温度も変わらない環境にいるため、徹底的に感覚的な違いがなくなるのが一番の原因だと著者は語ります。
徹底的に同じにするということを突き詰めていくと、それは頭の中にしかなくて、そこから出てくるのは同じもの、すなわちコピーです。
スマホの中身のパソコンの中身も全部コピーであり、いくらでも同じものをつくることができます。
同じものを以外は存在しないという世界を、知らず知らずのうちにつくり、それを経済的、合理的、効率的だと呼んで崇拝しているうちに、ふと「生きてるって、どういうことか」がわからなくなってくるというのが著者の考えです。
読みやすい構成でスラスラ読めると思っていると、ときおり飛び出す社会の問題点を突く深い洞察に驚くおもしろい対談です。
『「他人」の壁』
著者と精神科医の名越康文氏が、相手を理解するのを妨げる「壁」や理解することの本質である「気づくこと」を中心に語り合った対談本です。
わからなくてもいいから、同じ方向に進んでぶつからないように、相手の出しているサインに気づくことが重要だと著者は語ります。
「わかる」や「気づく」に悩んでいる人に対する処方箋として著者が提案するのは、「感覚を磨く」ことです。
それにはできるだけ多様な状況に身を置き、ふだん自分が行かない場所に行き、五感を刺激することが大切だといいます。
特に自然に親しむことで、「手入れ」と「コントロール」の違いがわかるようになるとも語ります。
相手を認め、相手のルールをこちらが理解しようとすることからはじまる「手入れ」と、相手をこちらの脳の中に取り込んでしまい、脳のルールで相手を動かせると考えてしまう「コントロール」のあいだの隔たりは大きいのです。
感性が磨かれた人はどのような行動をとるのか知りたい人のために、本書の中で著者がおすすめしているのは、小説『シャンタラム』です。
強盗で懲役20年の刑に服していた男が脱獄し、逃亡先のインドのスラム街で、無資格で住民の診療をおこなうことから始まる作品でドラマ化もされています。
上巻、中巻、下巻とボリュームがありますが、あっという間に読み終えてしまう魅力があります。
『シャンタラム』の日本語版は、著者が版元に翻訳するように働きかけたという本書のエピソードには驚きました!
感性を磨くということについての根本的なこととして、自分の人生にしっかり向き合うことを著者は強調します。
その人の人生というのを、1つの「作品」と捉える古くからの考え方はすごく大事なことだと話す著者の価値観に共感する方は多いのではないでしょうか。
『虫とゴリラ』
虫が大好きな著者と、霊長類学者・人類学者で特にゴリラの生態についての研究で知られる山極寿一氏による対談本です。
タイトルに現われているように、本書では人間とは違う生き物に執着して生きてきたお二人が考える、人間以外の世界観が語られています。
「第一章 私たちが失ったもの」「第二章 コミュニケーション」「第三章 情報化の起源」「第四章 森の教室」「第五章 生き物のかたち」「第六章 日本人の情緒」「第七章 微小な世界」「第八章 価値観を変える」という章立てで構成されています。
たとえば第二章では、言葉を使わない生き物との会話と、言葉を使った人間の会話の違いについて興味深い話が交わされています。
言葉は名前をつけることで、本来は「違う」ものを「同じ」カテゴリーに入れることを前提としているのに対して、自然界ではそもそも全部が違うものだから互いが違うものとしてコミュニケーションをしています。
できるだけ五感を使わないようにして違いを排除しようとする現代社会とは異なるルールであり、「違い」は感覚で知るものであることを忘れてはならないと著者が語る言葉の重みが感じられます。
第三章では、解剖学者として活躍してきた著者が「情報化する作業が手抜きになっている」ことに触れ、事態を憂慮する場面があります。
著者は解剖学を「人体を情報化する作業」と表現しています。
身体という得体のしれないものをわかってもらえるように「名前をつける」行為に価値を置いていた時代から、ビッグデータに象徴されるように、すでに情報化されたものを利用する時代に変わってしまっているという指摘には、目から鱗が落ちます。
「方法論が確立されているから問題ない」という考えが陥る落とし穴について、科学と宗教の違いを引き合いに語る著者の知性にも驚かされます。
人間以外の世界について考えてきたお二人は、人間がつくり上げた現代社会が失った身体性について憂えています。
本書には現代人が取り戻さなければならない「生物としての人間」の観点、自然の中で身につく感性についてのヒントがふんだんに盛り込まれています!
『まる ありがとう』
著者が長いあいだ連れ添った愛猫のまるについて綴ったエッセイです。
まるの写真が多くのページを割いて114枚も掲載されているので、心が休まります。
本書の表紙にある写真のように、「どすこい座り」をしているまるの風貌は、ふてぶてしいようで私たちに何かを問いかけている眼差しをしている気にもさせられます。
著者にとって、まるは「ものさし」であるといいます。
人間の常識にとらわれずに日々を過ごすのに、まるの存在は非常に大きかったのだろうと推察される表現です。
まるがいなくなって、「心にぽっかり穴があいた」という表現では足りない、言葉というのはことほどさように無力であると述べる著者の気持ちに共感を抱く方は多いのではないでしょうか。
『子どもが心配』
著者が都市化が進んだ日本の子どもが幸せになる教育について、精神科医、小児科医、研究者、学校経営者の識者4人との対談がまとめられています。
未来の宝である子どもたちが「生きていてよかった!」と思えるより良い社会にするには何が必要なのか、大人は何をしてあげられるのだろうかといったことを考えるきっかけになるアイディアが満載です。
子育て中の方や教育に従事されている先生、部下を持つビジネスパーソンなど、教育に関係するすべての方に読んでいただきたい一冊です!
本書の詳しい紹介については、こちらの記事をご参考にしてください。
『地球、この複雑なる惑星に暮らすこと』
漫画家・文筆家のヤマザキマリが「箱根昆虫館」の異名を持つ著者の別邸を訪れ、合計7回にわたって行われた対談がまとめられています。
ジャンルにとらわれず、どこに向かうともなく展開されるこの対談本は、どこから読んでもおもしろい内容です。
自身も昆虫好きであるヤマザキマリと著者の虫に関する話は、自然を自分と関係ないものとみなす都市化した人間の考え方や、人間の生み出してきた社会と深くつながっています。
自分が言語化できないことを言葉にしてくれる人や、わからないことを見抜いてくれる人がメディアでもてはやされる裏には、日本の特徴である「なる」論理が現代でも通用しているという見解には目を開かされます。
『ものがわかるということ』
「わかる」とはどういうことなのか、それが「わからない」。
編集者のこの質問に答える形ではじまったのが本書だといいます。
著者は若い頃、勉強すれば何でも「わかる」と思い、時間さえかければわかるようになるはずだと考えていました。
しかし八十代の半ばを過ぎ、人生を振り返ってみると、わかろうわかろうとしながら、結局はわからなかった、という結論に著者は達しました。
タイトルである「ものがわかるということ」に対して単刀直入な答えを見つけようとする方にとっては、本書は役に立たないでしょう。
しかし、「わかる」ということを改めて考えてみたい方にとっては目から鱗の視点が盛りだくさんです。
「世界をわかろうとする努力は大切である。でもわかってしまってはいけないのである。」
こう語る著者が「わかるとはどういうことか」を長年考え続けてきた思想が、本書にはまとめられています。
人間が日々変わり、情報は不変のはずなのに、両者が逆転して理解されている現代社会に生きる人々がものごとをどのように理解しているのか、自然を軽視した都市で生活することで何を見失っているのかを考えるヒントに出会える素晴らしい内容です!
『日本の進む道 成長とは何だったのか』
本書は著者と地域エコノミストで主著『デフレの正体』で有名な藻谷浩介氏の対談をまとめた作品です。
藻谷氏は平成大合併前の約3200市町村のすべて、海外114ヶ国を私費で訪れ、地域の特性を多様な観点から把握し、地域振興や人口問題に関して研究を重ねられています。
お二人の対談は、経済と政治、大地震への備え、教育問題、さらには日本人の生き方について、一般人にはなかなか考えられない観点で話が進んでいき、おもしろい話ながらも立ち止まって考えてしまう内容に富んでいます。
たとえば、戦争末期ではバケツリレーで火を消しながら本土決戦していた状況を「おかしい」と思いながらも、それを訂正する機構がないのでみんなが「人格分裂」していたという話があります。
ここには、日本人が持つ特性が含まれていて、現代の大地震への対策や深刻な少子高齢化問題をはじめとする緊急度も重要度も高い問題に対し、具体的な手を打つのではなく考えないようにしていることはその一例といえそうです。
著者は、「本気で考えるためには本気で困らなければ無理で、何とかなると思っているうちはダメなものだ」というスタンスで、「みんなが気づくのを待つしかない」と語りますが、本書をはじめ数々の作品でご自身の見解を何度も書き記しているところをみると、それでも話しておかずにはいられないことがあるのだと感じさせられます。
本書は藻谷氏のリードもあり、経済問題にも突っ込んだ対談がおこなわれているので、他の作品ではお目にかからない著者の見解を読むことができます。
『日本の歪み』
本書『日本の歪み』は著者と脳科学者の茂木健一郎氏、批評家の東浩紀氏による鼎談本です。
著者いわく、本書には近代以降の日本社会の歪みに関する問題点がほぼ出尽くされているといいます。
本来は割り切ることのできないものをシンプルな物語に仕立て上げ、ものごとを進めてきた結果として日本は様々な矛盾を抱えている。
世界を単純に捉えてわかりやすく把握することを拒否し、複雑なものを複雑なものとして考えているお三方は、本書を読むとわかるように、現代の日本社会にそれぞれ居心地の悪さや生きづらさを感じています。
その違和感は何なのかが、「明治維新と敗戦」「憲法」「天皇」「経済停滞」「少子化」などの視点で語り合われており、非常に興味深い内容です。
本書は日本社会が抱える問題点が数多く語られると同時に、お三方の人生における価値観も垣間見ることができます。
問題は常に向こうから来てくれるものだと思うのは怠けている証拠で、本気で生きていないという著者の意見にお二方が共感されているのは印象的です。
『生きるとはどういうことか』
本書は、2003年以降に発行された新聞・雑誌・印刷物所蔵のエッセイから単行書未収録作品が厳選され、1冊に編まれたものです。
著者は編集されたゲラを読んで、20年前に書いた自分の文章は「今ならもっと気を抜いて書くところも、気を抜いていない。ただまっしぐらに思いを述べるという点が目立つ」と振り返っています。
「人生」「環境」「思考」「脳・意識」「世間」「身体」「教養」というカテゴリーに分けられ、自然に対する人間の向き合い方、「自分は変わらないもの」という近代的自我への批判、個性は心ではなく身体に宿っていることなど、心が洗われる論考が数多く収められています。
「教養」の中で、古典を読むことを強調して推奨しているのは、著者のエッセイとしては珍しいと思います。
私も年寄りになったからいう。古典は読むべきだし、読む力をつけるべきである。
それには自分で読むしかない。
他人をアテにしてもムダである。
まして学校では、ほとんどなにも教えてはくれまい。
教えてくれたら、それこそ事故みたいなものであろう。
(中略)
私が解剖学を学び始めた頃、そんな古臭い、というイメージが世間ではふつうだった。
「そんな古臭い」学問を学んで、私は食うに困ったか。
おそらくまったく逆だった。
解剖で学んだ方法を応用するだけで、六十代の半ばを過ぎても、十分に仕事をしていける。
はやらないものをきちんと身につけることは、長い目で見れば、いちばん安上がりの自己教育である。
不易を大切にすることで、刹那的な流行に押し流されずに立ち居振る舞えるのだと戒められる言葉です。
本書には、本の形で出版された他の作品ではなかなかお目にかかれない著者の言葉に出会うことができます。
読み終わって、最後に「教養」に関するエッセイを収めた編集者の思いにも心が動きました。
『ヒトの幸福とはなにか』
幸福、風景、虫、文化・伝統、犬と猫、教育といった様々なテーマで著者が書いた、単行本初収録のエッセイ集です。
タイトルに冠されている「幸福」について、本書の冒頭から目を開かされます。
著者は小学校2年生で終戦を迎え、ものがないのが当たり前の日常を送りました。
現代から見ると、食べ物をはじめ生きるために必要な衣食住を確保することに懸命になっていた時代で、さぞかし大変だったのだろうと感じますが、「自分だけないと不幸だが、みんながないなら別に不幸ではない」と著者は語ります。
飽食の時代になり、デジタル社会も整備されている現在は、過去と比較して進歩している。
日々の生活も豊かになっているはずだが、何だか生きにくいと感じている人は多いのではないでしょうか。
何かが欠けているのだが、それが何なのかはっきりせず、ないものが見えないために暮らしにくい現代。
本書『ヒトの幸福とはなにか』では、現代で流行している価値観を揺さぶる著者の考えに触れることで、自分の幸福、日本人の幸福、文化の異なる人の幸福をあらためて考える機会が得られます。
言葉で説明できることだけを信用する、個性を過度に意識する、自分は変わらないと信じる。
こういった凝り固まった価値観を壊したいのであれば、本書はそのきっかけになる言葉が詰まっていると思います。
『こどもを野に放て!』
本書は登山者用地図アプリを提供する「YAMAP」を創業した春山慶彦氏が、解剖学者である著者、生命誌研究者の中村桂子氏、小説家・詩人の池澤夏樹氏とそれぞれ対談した内容をまとめた作品です。
冒頭に著者との対談が収録されており、「自然の中で身体を動かすだけで無意識に学んでいる」と銘打ってあります。
20万年におよぶ人類の歴史の中で、人間の身体はパソコンやスマホを使うためではなく、自然の中で生き抜くためにつくられています。
便利になった社会で、現代人は「感覚から入るものを軽視しがちで、勉強すれば何でも頭に入ると思っている」と著者は語ります。
本当はそれ以前に自然の中で感覚を磨くことが非常に重要であり、感覚や感性が十分に養われていれば、知識はあとからでもキャッチアップできるといいます。
五感を使って入力し、それに反応して身体を動かすのが出力で、小さい頃からその入力と出力を繰り返していくことで脳内にあるルールができ、それが学習の始まりだというのは、子育てや子どものふるまいをよく観察している方にとっては腑に落ちる話ではないでしょうか。
自然体験で身につく力は数値で測ることはできず、思い通りにならない自然を相手に地道な努力をしたり、予測できないことを受け入れ、うまく自分を納得させるには自然に親しむことが肝心だという著者の言葉は非常に印象的です。
同時に、「ああすれば、こうなる」社会の中では、著者がこのように語らなければ自然になじみのない人は重い腰を上げないという皮肉めいた現実もあるのだと感じられます。
春山氏がおこなった中村桂子氏、池澤夏樹氏との対談もおもしろい内容が詰まっています。
中村氏が手掛けた「生命誌絵巻」の写真が本書に掲載されていますが、生命の歴史が一望できるだけでなく、人間は生き物であるという当たり前の事実に気づかされずにはいられない素晴らしい作品に心を奪われます。

池澤夏樹氏との対談では、春山氏が写真家を志してアラスカに移り住んだきっかけとなった星野道夫氏にまつわる話に引き込まれます。
星野道夫の写真や文章だけでなく、その生き方や生きることに対する純粋さ、友人であった池澤氏とのエピソードなど星野道夫ファンにはたまらない内容です。
本書の巻末には、春山氏が自然観を考える上で道しるべとなる本が紹介されており、『旅をする木』が含まれています。
自然に対する星野道夫の向き合い方が読みやすく書かれているだけでなく、自然とはどういうものなのかを立ち止まって考えさせられる作品です。
おわりに
今回は解剖学者の養老孟司のおすすめ本をご紹介しました。
昔に出版されたものから新刊に至るまで、読めば読むほど著者の深い思想におどろき、読むたびに新しい発見があります。
楽しく生きる知恵が詰まった著者の作品をぜひ読んでみてください!
「アマチュア読者の楽しい読書会」を開催しています。
読んでおもしろかった本について楽しく語りあう場なので、ご興味のある方はこちらもチェックしてみてください!



































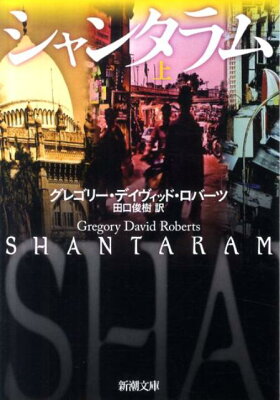
















コメント