「寄生虫」と聞くと、ネガティブな印象を受ける人が多いだろう。
映画やアニメの影響で、ヒトの体内に棲みついてその数を増やし、宿主をコントロールするイメージがあるかもしれない。
本書ではリアルな寄生虫が学問の観点から語られる。
複雑な生活史を繰り広げ、宿主なしでは生きられない、ときに宿主に頼らない時期も経ないと生きられないのが寄生虫である。
寄生虫はここまで生き残ってくるために、体の形、消化器の仕組み、エネルギーを生む仕組みなどいろいろな工夫を凝らしてきた。
さらに、外来者を必死に排除しようとする宿主の複雑な免疫をなだめすかし、寄生虫は安住の地を得るのである。
寄生虫には、生き物として生き残るための様々な知恵が詰まっている。
そもそも寄生とはいったいどういうことなのだろう。
本書によると、他の生物の中に入って、あるいは表面にいて、居場所を与えられるあるいは侵入して、食料(栄養)をもらってあるいは横取りして生きている生物の現象を指すという。
寄生する生物を奇生体(寄生虫)、それを受け入れる側を宿主と呼ぶそうだ。
この「宿主」という言葉について、本書にはこう書かれている。
「寄生虫はひとりで暮らしてはいけません。宿主―「しゅくしゅ」と読みます。なかには「やどぬし」などと読む人もいますが、寄生虫フリークのあなたは、間違っても「やどぬし」などと叫んではいけません。「やどぬし」では旅籠のオヤジを連想してしまいます―があっての寄生虫です。」
異なる種類の生物が一緒に生活するパターンとして、共生と寄生がある。共生は相利共生と片利共生に分かれる。
相利共生は、AがBから何らかの利益をもらい、BもAから何らかの利益をもらう関係をいう。
たとえば、映画「ファインディング・ニモ」でおなじみの、カクレクマノミとイソギンチャクの関係がそうである。
カクレクマノミはイソギンチャクから隠れ家を提供してもらい、イソギンチャクはカクレクマノミにつられてやってくる同じくらいの大きさの魚を捕食できる。
カクレクマノミは特殊な粘液をからだにまとっているので、イソギンチャクの刺胞の毒を避けることができるのだ。
他にもヤドカリとイソギンチャク、牛とその胃の中にいる微生物は相利共生の関係にある。
片利共生は、AはBから利益をもらうが、BはAから何の利益も受けられない関係のことをいう。
大きなサメとコバンザメがわかりやすい例だろう。
本書では、日々の生活で遭遇する寄生虫の例が多数挙げられており、寄生虫フリークでなくとも楽しめる内容になっている。
コンタクトレンズで角膜炎を引き起こすアカントアメーバ、ブタから感染する有鉤条虫(だから豚肉にはよく火を通す必要があるのだ)、魚介類に寄生するアニサキス(最終宿主のクジラやイルカの胃に寄生するまで長い旅を辛抱強く続ける)など、「そういうことだったのか!」と膝を打つトピックが盛りだくさんである。
寄生することによって宿主は害を受けることが多い。
ただ、害がひどく栄養をもらっている宿主が死ぬとそのまま寄生を続けることができなくなる。
代を重ねて寄生していくうちに、害の少ないものの方が残りやすく、害がだんだん減ってくる。
究極的には害がなくなることになるので、寄生というよりも共生に近い状態になる。
本書を読んでいると言葉の端々から、「この人たちは本当に寄生虫が好きなんだろうなぁ」と思わずにはいられない。
ただ、写真やイラストも多数掲載されており、通勤電車で読むには、安定した宿主を探し続ける寄生虫と同じくらいの心がまえが必要である。
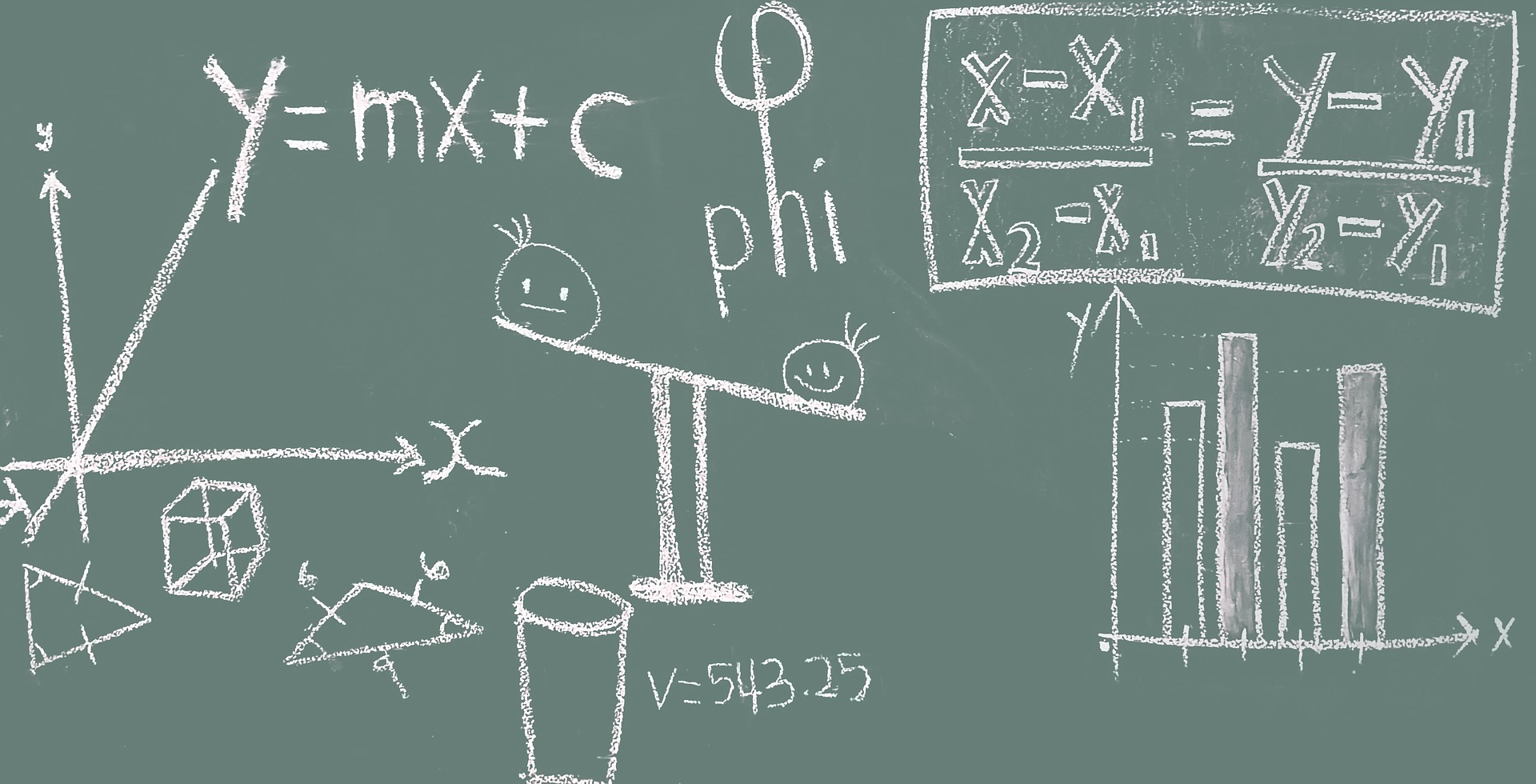


コメント