こんにちは、アマチュア読者です!
今回ご紹介するのは、長嶋修、さくら事務所『災害に強い住宅選び』です。
地球温暖化の傾向が続き、平均気温が上昇し、二酸化炭素濃度も高まっている今日においては、想定外の自然災害に目を向けざるを得ず、日々の気象情報に関心を寄せる方も多いと思います。
国土交通省も今世紀末には100~200年に一度起きる豪雨の降雨量は、20世紀末の1.1倍になり、100年に一度の豪雨は50年に一度起こることになると試算しています。
つまり、これまでの防災計画では対応できない豪雨に襲われる頻度が高くなるとみているのです。
全国のあちこちにあり、どれを選ぶのかは自己責任であり、経済的にも人生で一番の買い物といわれる不動産。
選択肢は膨大にあるものの、不動産を購入した経験のない多く方にはノウハウがなく、一瞬の閃きを頼りにし、不動産屋さんの言葉に後押しされて購入に踏み切る方もいると思います。
しかしながら、自然災害(あるいはそれに関する人災)が不動産に及ぼす損失は想像以上であり、どの物件を選ぶかが命と資産を守る分岐点となるといっても過言ではないでしょう。
経済的な影響も無視することはできず、たとえ保険をかけていても家屋が全壊とみなされず、半壊と判定されるケースが多いこともニュースで目にする機会が増えています。
「自然災害が増える中で、どのように家を選べばよいのか?」
「自然災害に強い住宅とはどのようなものなのか?」
本書『災害に強い住宅選び』では、こうした想定外の自然災害リスクが高まる時代に、どのように不動産を選べばよいのかを不動産のプロである著者たちが解説しています。
多くの人はハザードマップに無頓着
不思議なことに、浸水の可能性がある地域は、そうでないところに比べて地価(不動産価格)に大きな違いが出ていないといいます。
その理由は、「多くの人がハザードマップなどの災害関連情報に無頓着」だからです。
著者は2019年9月5日に発生した台風15号や、2019年10月12日の台風19号における住宅被害を現場取材しています。
被災地の住民に話を聞く中で、多くの方が「ハザードマップを見たことがない」と回答していたといいます。
ハザードマップは、河川氾濫による洪水や地震による津波、土砂災害、火山噴火など、さまざまな災害被害を予測し、その被害の範囲を地図上に示したものです。
自分の住んでいる地域や住まい探しで検討している地域をインターネットですぐに閲覧でき、非常に便利です。
2019年の台風19号などの影響を鑑みて、2020年8月に国土交通省は『水害ハザードマップの説明の義務化』を施行しました。
そのため、不動産のオーナーは重要事項説明の時に、不動産の法律に詳しくない一般の方のためにハザードマップの説明が必要になりました。
しかし、事前に下調べをせずに入居前に説明を受けても「いまさらゼロベースで検討し直すのは大変」と思い、そのまま購入してしまう方もいるようです。
本書ではハザードマップの重要性を説くとともに、使い方もわかりやすく書かれています。
地盤や土地の歴史は「国土地理院地図」
住んでいる場所がゲリラ豪雨などに見舞われ、短時間で集中的に雨が降った場合、排水処理能力が追いつかず、洪水になる可能性があります。
たとえば東京都の場合、1時間あたりの排水処理能力は50mm程度となっている自治体が多いものの、ゲリラ豪雨はこの水準を大きく上回ります。
そうなると、地域の相対的に高いところから低いところに雨水が集中し、冠水してしまうおそれがあります。
地震に関しては、地盤が強いのかどうかが災害対策を考慮した住宅選びのポイントであると著者は語ります。
地盤が弱くて揺れやすい地形の場合、地盤の固いところに建つ建物に比べて揺れやすくなります。
場合によっては、建物の耐性を高める工事が必要になります。
もし液状化した場合、建物は無事でも上下水道など地下に敷設されているインフラが毀損する可能性があるといいます。
本書によると、地盤や土地の歴史を知るには「国土地理院地図」が便利だといいます。
実際に使ってみると、気になる土地についての知見を深めることができます。
年代別の空中写真や標高・土地の凹凸、土地の成り立ち・土地利用など、その土地の歴史を短時間で視覚的に把握することができるので重宝します。
たとえば、大雨が降るとよく浸水する地域を衛星画像で確認すると、その地帯がかつて河川だったということもわかります。
「不動産は一に立地、二に立地」という言葉があらわすとおり、本書を読むと住居選びにおける土地の重要性を強く感じます。
減災のための事前対策
本書では住宅選びに関連して、災害に遭ってしまった場合でも被害を軽減できる対策が紹介されています。
中でも対策しやすいものとして、自宅に防災備蓄品を十分に用意しておくことが推奨されています。
当たり前のことのように思えますが、実際に防災グッズの準備に関する2024年のアンケート結果(会社によってバラツキあり)では、食料品などの備蓄はしているものの、対策としては十分ではないと考えている人が多いようです。
一戸建ての場合はもちろん、マンションにおいても防災備蓄品がほとんど準備されていないケースや、準備されていても分量が不十分なケースがあるといいます。
そうした場合に備え、防災備蓄倉庫の中身を確認し、自分で何をどれだけ用意しておくべきか把握することが重要だと著者は説きます。
一般的に、自宅で備蓄しておくと望ましいとされるものとして以下が挙げられています。
・飲料水(1日あたり1人3リットル×人数分を1週間分)
・簡易トイレ(家族の人数分を1週間分)
・懐中電灯
・携帯ラジオ
・電池
・モバイルバッテリー(手動携帯充電器)
・卓上カセットコンロ
・カセットボンベ
・固形燃料
激甚災害によって、食べ物や飲み物が手に入らなくなる事態は想像しづらいかもしれませんが、物流がストップすれば食料品がコンビニやスーパーの店頭に並ぶことはなく、長期間の閉店を余儀なくされる可能性があります。
上記とは別に、緊急時の持ち出しグッズも考慮しておく必要があるので、災害のための事前準備は想像以上に物量が多くなるものなのだと感じます。
同時に「防災に対して本当に必要なものは何なのか」についても考えさせられます。
また本書では、付録として減災のためのチェックリストも掲載されており、コンパクトにまとめられているので要点をつかむのに役立ちます。
おわりに
今回は、長嶋修、さくら事務所『災害に強い住宅選び』をご紹介しました。
想定外の自然災害が毎年のように発生する時代に、わたしたちは住まいとどのように向き合うべきなのかを不動産のプロが指南しています。
ハザードマップの使い方、土地の歴史を知ることの重要性、一戸建てやマンションを購入する際の注意点、減災のための事前対策など、自分の住む地域を検討する上で大切な観点が盛りだくさんです。
住宅選びを真剣に考えたい方には非常におすすめです。
ぜひ読んでみてください!

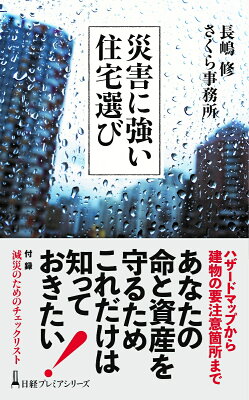


コメント